この記事は「引継ぎの仕方」について、やってよかったことを書きました。
具体的すぎる(?)アドバイスと、引継ぎ時に必要な心構えの話をメインにしています。
ついでに自分の仕事レベルも向上し、復帰後に自分が引継がれる立場になった時にも便利な「手順書」の作り方についてくわしく書いています。
とくに初めての「引継ぎ」は緊張します。
さらに産休前の引継ぎは自分の都合で行うものなので、相手に迷惑をかけないかドキドキしますよね。
入社したばかりの新人さんや年上の先輩。
相性の悪い方だとさらに気を遣うと思います。
でも、だいじょうぶ!
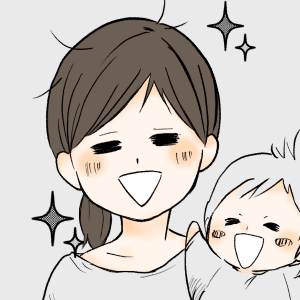 育
育バッチリ引継ぎを終わらせて、きもちよく産休にはりましょう♪
引継ぎの重要ポイント
妊娠おめでとうございます。
具体的な「引継ぎ書」方法より先に大事なことを書かせて下さい。
※精神状態がいい方は、『引継ぎ書の作成手順』まで読み飛ばしてもらって大丈夫です。
今の環境と職場の人間に感謝しよう
引継ぎの成功は「感謝のきもち」が相手に伝わっているかどうかにかかっていると言っても言い過ぎではありません。
「働ける環境にいる」って素晴らしいことですよね。
少なくともわたしたちは「仕事ができる程度には健康」で「給料」をいただいて生活しています。
同じように働いてくれる人が複数いるから、会社として成り立ちます。
あなたのする仕事に価値が生まれるのは皆のおかげです。
感謝したくない人も中にはいるかもしれませんが(笑)
ただせめて自分の仕事を引き継いでくれる相手へは、感謝の心を忘れないで下さい。
あなたが産休の間にできないことを補ってくれる人です。
権利として「産休・育休制度があるんだから。業務を負担するのが当たりまえ!」と思えば、しっかりそれが相手に伝わります。
「わたしが働いていない間も会社を支えてくれる人がいる。だからゆっくり休めるんだ」と思えていることが引継ぎをスムーズに行う鍵です。
健全な心からストレスフリーを手に入れる
感謝の気持ち。なるほど
バッチリよ!となれば、引継ぎ相手に何を思うでしょう。
「引継ぎの相手が困らないように」
「出来るだけ分かりやすく伝えよう」
そう思えたら、引継ぎは 90% 上手くいっています
「どうせ引き継ぐんだから適当でいいや」
「分かりくいけど、なんとかするでしょ」
この考えで業務を引き継ぐと、引継ぎ相手より自分が困ることになるかもしれません。
- 引継ぎが進まず、イライラ。
- 引継ぎ相手からの不満を告げ口したり、されたり。
決して気分のいい状態にはなりません。
この状態でモヤモヤと産休に入るのは避けたいですよね。
出来るだけ「引継ぎ相手の負担を減らしたい」この考えで行動します。
引継ぎ書の作成
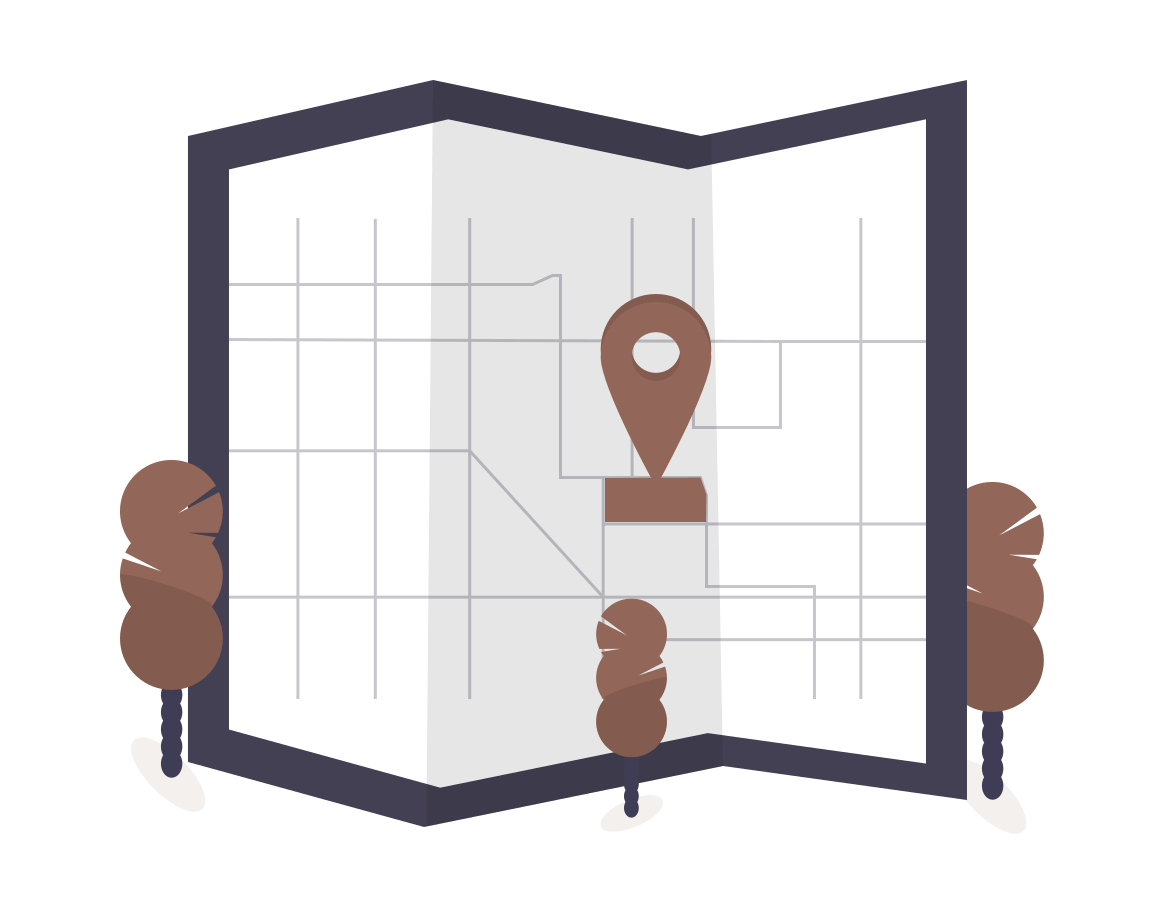
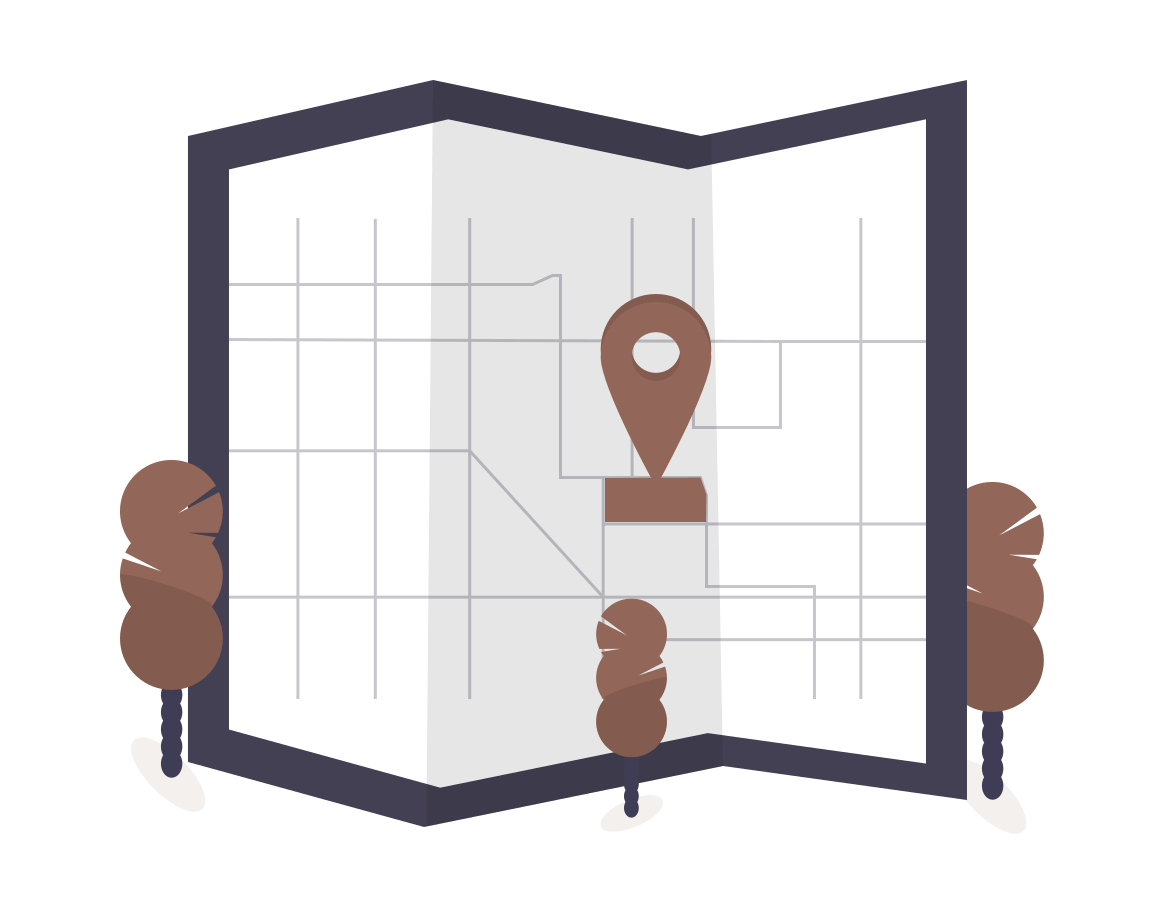
引継ぎ内容は「文書」で残します。
口頭だけの説明はなるべく避けます。
「言ったor言わない」の不毛な冷戦を生まないためにも、必ずテキストで残しましょう。
これから用意する「引継ぎ書」が出来てから、引継ぎを開始することになります。
余裕をもって作成したいので、妊娠が分かったタイミングですぐに始めるといいです。
これから説明するやり方は、早く始めれば始めた分だけ、自分への恩恵が大きくなります。
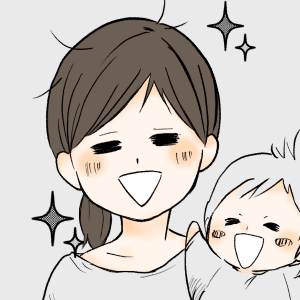
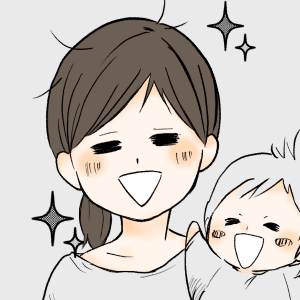
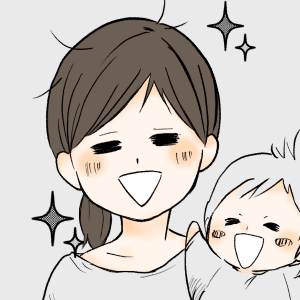
妊娠や引継ぎが ある・ない にかかわらず
作ってもいいくらいオススメです
1「作業内容」の書き出し
まずは行っている業務を「リスト化」してください。
毎月発生する「定型業務」と
都度発生する「非定型業務」に分けて考え、書き出すと書きやすいです。
(場合によっては、「年間行事」なども組み込みます。)
書き出してみると「意外と色々こなしてるな~」と思ったり
「あれ?もっとあると思っていたのに、項目にすると意外と少ない」と思うかもしれません。
リストの書き出しが終わったら、
「この作業は今後も本当に必要だろうか?」という視点で全体を眺めてみてください。
もし、そんな内容があれば上司に相談します。
古くから習慣でこなしている業務の中には、実は「誰も見ていないデータ」「必要ない作業」という場合が多々あります。
特にご自身や上司が「だれのためにやっているんだろう?(説明できない)」という作業は、引継がれる方も迷惑なので、潰しておいてください。
なくして構わない作業は、積極的になくします
5分で終わるような単純作業でもなくします
チリも積もれば山となる。
1つでもなくなると引継ぎも楽ですし、晴れ晴れしますよ。笑
2「手順」通りに書き出す・見直す
リストが完成したら、作業の内容を普段自分が行う通りの順番で箇条書きにします。
この時、
「どうも説明が難しいな。書きにくい」と感じたならば、仕事の手順がよくない可能性があります。
シンプルに人に教える為には、どの手順を直せば良いか、どの点が引っかかるのか。
改善の余地が見えてくるはずです。
箇条書きで端的に書けるところまで落とし込みましょう。
実際に自分が書いた手順通りに作業がすすめばOKです。
3「ファイルの場所」を記載する
前任者がいなくなって一番あるあるな問題が「目的の資料がどこにあるか分からない」
ファイルの場所は、少し触らなくなるとすぐに忘れます。
「分かりにくい名前」や「ファイルにラベルがない」は論外です。
いい機会なので、すぐに対応しておきましょう。
「紙ファイル」「電子ファイル」共に
「手順書」に所在を書いておくと、自分が復帰した時にも役に立ちます。
4「困った時の連絡先」を書いておく
どんなに手順書で説明したつもりでも、判断に迷ったり、イレギュラーなことは起こります。
そんな時は、困った時はこの人に頼ってね。相談にのってくれるよ。という人の名前が書いてあると安心です。
相談相手として記載した人には、あらかじめ「何かあった時は○○さんが頼りにしますので、相談に乗ってください」と両者へ同時に根回ししておくのがおススメです。
「ちゃんと引継ぎされてるんだな」と関係者も安心してくれますし、「え?知らないよ」と言われるのを防ぎます。
5「完成した引継ぎ書は上司と確認」する
こうしてできた『引継ぎ書』は下記のようなイメージです。
| 作業項目 | 概要 | 手順 | 連絡先 | 保管場所 |
|---|---|---|---|---|
| 【毎日の定型業務】 | ||||
| ゴミ拾い | 社内美化の ために毎日 活動! | ①軍手をはめる ②ごみを見つける ③拾って指定袋へ ④××に持ち込む | ××× 内線 1234 | 軍手は倉庫の4段目 袋は倉庫の3段目 ××は:URL |
| 【毎月の定型業務】 | Excel 「●sheet」参照 | ファイルのURL フォルダの場所 | ||
| 【毎年の定型業務】 | ||||
| 【発生都度】 | ||||
| 社長の小言をきく | 重要! | ※別途資料有 |
これに備考欄を設けて注意事項やアドバイスを書き添えます。
実際の作業に合わせて項目をつくってください。
とにかく分かりやすく、漏れなく書きます。
どんなにあほらしいと思う小さな雑用でも、自分が率先してやっている仕事は書いておいた方がいいです。
上司が見たら「こんな事もやってくれていたんだ」という発見がありますし、きちんと引継いでくれているんだなと安心感が増します。
「これがあれば私の業務は網羅される」という状態になったら引継書は完成です。
仕事を引き継ぐ
引継ぎの段取りができました。
いよいよ引継ぎです。
ここで大切なことを確認します。
誰に引き継ぐのか
手順書を作る段階で、あらかじめ引継ぎ先が決まっていれば問題ありません。
また、引き継ぐ相手が一人の場合は、比較的楽です。
問題なのは、「この部分はAさん」で「こっちはBさん」「そしてCさん」となる場合です。
この時に「引継書」が大いに役に立ちます。
リスト上に「これとこれはAさんに引き継ぎます」とチェックができるからです。
引継ぎ先が2人以上の時は、誰に引き継ぐかも記録しておきましょう。
「これはAさんが担当するんじゃなかったんですか?」
「わたしはBさんだと思っていました」
などのやり取りがなくなります。
「誰に何を引き継ぐのか」上司と確認しておいてください。
引継ぎ相手の時間を確保
引継ぎの時間を確保する必要があります。
あなたの為だけに補充した新人さんである場合を除き、相手にも自分の仕事があります。
「時間が出来た時によろしく」では引継ぎが進みません。
突発的でかつ緊急性を要する案件が入らない限り、あらかじめ決めた時間内で行います。
日時はなるべく相手の都合に合わせましょう。
発生しなければ教えづらい業務は「この時になったら声をかけるのでよろしくお願いします」と伝えておくとスムーズです。
引き継ぐときの具体的なやりとり
まず初めにやることは、リスト化した「引継書」を見せることです。
引き継がれる側の立場になると「どの程度のボリュームで仕事が回ってくるのか分からない」これは結構ストレスになります。
最初にリストで全体像を把握できれば、この後の具体的な話を安心して聞いてくれます。
また1つの作業にかかる「目安時間」を伝えるとより親切です。
リスト上のすべての業務が引継ぎ対象ではない場合、
「Aさんにはリストのここからここまでをお願いします」と伝えればいいです。
分かりにくくなるようなら、その人専用にリストを編集してもいいです。
そして実際に、引継ぎ業務の実践を始めたら、今やっている内容は手順書のココに書いています。と伝えましょう。
相手がメモを取る必要がないので、話に集中しやすいですし、振り返った時に記憶が定着しやすいです。
手順書に書かれていること以外でメモを取りたい場合もあるので、手順書へ直接書き込める媒体をあらかじめ相手に渡しておくのをオススメします。
それから引継ぎ中に「質問」があった場合、「書き足した方が良い」と判断した内容は、手順書に加えましょう。
人間は忘れやすい生き物です。
口頭で補足説明したにも関わらず
あとあと「聞いてない」「知らなかった」と言われるのも悲しいですもんね。
最後に自分へのメリット
これを読んで「ちょっと大変そう」「めんどくさい」と思ったでしょうか(笑)
「なんだ、こんなことね。」と思ったかもしれません。
上記は、自分が引き継いだ経験を元に書きました。
引継ぎをやって一番良かったことは「自分の業務の棚卸ができた」点です
上司と業務内容について見直すキッカケにもなり、自分が楽になった改善もたくさんあります
なによりこの手順書に自分の業務の全てが集約されたので、これさえ振り返れば、対応の抜け漏れや、「次に何をしよう」という迷いがなくなりました。
「これがあった」「時間的にこれをしよう」とすぐにピックアップできるようになったからです。
また手順書には、関係する電子ファイルの類を全てヒモ付けました。
1つのファイルさえ開けば、全てにアクセスできるという状態です。
場所を覚える必要がなくなり、ファイルを探す工数も減りました。
作業効率が上がると、本来自分のやりたい仕事に集中できる時間が増えます。
その結果、仕事にやりがいを感じ、もっと仕事が好きになりました。
そして自分が育休・産休から戻ってきた時。
前の業務を変わらず行うのであれば、引継ぎ相手から同じように「改定された手順書」を貰えばいいので、変化点が分かりやすく楽でした。
わたしが育休中にこの手順書で変わった点はありますか?と聞けば、相手も答えやすいですよね。
「ここ」と「ここ」です
「この作業はなくなりました」
自分の作った手順書で説明してくれるので、業務の記憶がよみがえるのも早かったです。
ポイントをまとめると
- 引継ぐ相手へ感謝
- 業務の棚卸
- 不要な業務はなくす
- 説明できない手順は見直す
- 作業内容をリスト化する(必ず文書化!)
- 上司と情報を共有する
- 復帰後も仕事がしやすいよう情報整理をお願いしておく
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
ツールは時代や環境によって変化するモノなので、あえて具体的な名称を避けましたが
ついでで書いておくと、私の職場ではメインツールがMicrosoft『Excel』でした。
手順書も何もかもがExcelです。笑
今は便利なツールがあふれていますね♪

コメント